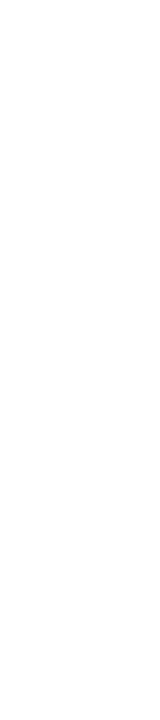緊張状態を解くマインドフルネス
- 婚活のコツ
- お見合い
- 自分磨き
目次
- キーワードは「いま、ここ、からだ、やさしさ」
- 「いま、ここ、からだ、やさしさ」の意味
- どのように行うのか(1)準備運動
- どのように行うのか(2)座り方
- どのように行うのか(3)呼吸に注意を集中します
キーワードは「いま、ここ、からだ、やさしさ」
マインドフルネスは「いま、ここ、からだ、やさしさ」のキーワードで実践できます。
比較的シンプルにこのキーワードで実践できるマインドフルネスをご紹介します。
本格的に、その効果を実感するのであれば相応の努力は必要です。
投資を考えてください。1万円を1年後に10万円にする投資は難しいでしょうが、100万円を1年後に110万円にする投資はありえるでしょう。
マインドフルネスも同様です。1万円分の努力をしても1年後に10万円分のリターンはありません。このことは経験から確実に言えます。
8週間のマインドフルネス実践プログラムであるMBSR、MBCTも静座して行う瞑想の時間を1日1回45分としてます。それ以外にも行うことがあります。45分という時間は、座禅の1柱(線香の燃え尽きる時間)に範をとっているようです(マインドフルネスはもともと仏教瞑想に範をとっています)。
たとえ話に戻ると、100万円分の努力をすれば1年後に10万円分のリターンは容易に得られると言えます。
とはいってもいきなり100万円の投資はできないよ、というのもごもっとな意見です。
そこで一番シンプルな、マインドフルネスを体験できる実践と考え方をお伝えいたします。
「いま、ここ、からだ、やさしさ」の意味
マインドフルネスは、人は「いま、ここ」に居ないこと=「現在」に注意が向いていないことが多く、それによって多くの不都合、いわゆる心理的な困難が生じると考えます。
自分が「いま、ここ」に居ない、ということを言い換えると、「心が急き立てられるように毎日を送っていて、自分の自由な選択による生活ができていない」と言い変えられるように思います。
さらにわかりやすく言うと、自分の今現在における自由な意思によってではなく、「習慣的な自動操縦状態」で生活している、ということになります。
「いま」にいない、ということの意味は、今現在のことではなく、「いま」ではない過ぎ去った過去を悔やんだり、これから先におこるであろうことを「いま」考えていて、それらのことが心の大半を占めている、ということです。
「ここ」にいない、ということは、今自分に起こっている感覚や思考に注意が向かっておらず、「ここ」つまり今の自分の体の感覚や目の前にあることに注意が向いていない、ということです。
マインドフルネスが前提としている考え方は、人の心の大半は、「いま、ここ」にないことに向けられている、と考えます。
人が、自分の体の感覚であろうと外部の出来事であろうと、「直接」感じ取ることが出来ず、感覚器官から得られた刺激を脳が処理して「イメージ」として再構成して認識しているという認知構造を持っている以上、このようになることは致し方ないことだと言えます。
人の心の大半が、「いま、ここ」にないことで占められている、ということは、「いま自分が感じている感覚」との接点を失っている、ということになります。
「いま自分が感じている感覚」との接点を失っていると、「いま、ここ」に無いこと(そのほとんどは今、自分でコントロールできないこと)を考えて、それに伴い感情が生起し、感情の生起により体に緊張をもたらし、結果としてエネルギーを消費してします。
わかりやすく言うと元気がなくなります。
生起する感情は、後悔や不安であることもあるでしょう。
後悔や不安は体に緊張をもたらし慢性化すると不具合を引き起こしかねません。この考え方は、認知行動療法を創始したアーロン・T・ベックの「認知モデル」の考え方です。
しかしそれらは、今ここに無いことです。今ここに無いことを考え、後悔や不安が生起しエネルギーを消費し、元気をなくしてしまっていることになります。
「いま自分が感じている感覚」との接点を失っていると、たとえば不安等のストレスに対して、適切に対応できず、効果的ではない習慣的な対応をしてしまうことにもなりがちです。
そこで、自分の体、そして心に注意を向ける能力を開発することによって「いま、ここ」に注意集中する=「マインドフルに対処する能力」を開発し、自分の体の状態、心の状態を知ることにより、体の緊張やそれをもたらしている不安や心配から、自分を解放する手掛かりがえられるでしょう、という観点から生まれてきたのがマインドフルネスです。
マインドフルネスは、当初、慢性疼痛患者等の(心的)ストレス低減法として開発、実施されてきました。これがJ.カバットジンが創始した「マインドフルネスストレス低減法」MBSRの始まりです。
そしてMBSRに触発されて創始され、マインドフルネス研究を飛躍的に盛んにしたものが「マインドフルネス認知療養」MBCTです。
双方ともに、ストレスやネガティブな思考から解放されることを通じて、ウェルビーイングを実現することをゴールにしています。この辺りの経緯については、下記ブログをご参照ください。
https://cometolife-kekkon.jp/staffblog/mindfulness-basic1/
「マインドフルに対処する能力を開発することで、不適応やストレスから自分を解放する」ことによってもたらされる創造性の涵養などに着目して、能力開発や企業内教育訓練にも取り入れられているようです。
過去のことや、将来のこと、今、目の前に無いことを考えると、それに伴い感情が刺激されます。感情が刺激されることで不安や後悔といった感情が活発になれば、思考に影響を及ぼし、自由な思考は阻害されます。自由な思考が阻害されれば、創造性が発揮することは難しくなります。
それゆえ、「いま、ここ」に注意集中する「マインドフルに対処する能力」を獲得することで、「いまこ、こに」に無いことを考えることで引き起こされる感情に影響されない思考を実現する「トレーニング」を行い、それが結果として創造性や問題解決能力の向上につながります。
そして「いま、ここ」に注意集中するために「からだ」への「注意集中」という方法が登場します。
『人の心の大半が、「いま、ここ」にないことで占められてい』て、『「いま自分が感じている感覚」との接点を失っている』のであれば、絶えることなく行われている呼吸への意識集中を通じて、体の感覚への接点を強化することで、「いま自分が感じていること」をよりダイレクトに知ることができるよね、そうすれば、いまここに無いことを考えていることによる不適応や不安などのストレスは停止するから、どのように対処したらよいか、いまでの考え方とは違う考え方、ヒントが得られるよね、ということになります。
別の考え方でいえば、人が本来持っている「レジリエンス」を強化する環境を作ることです。
もう少し詳しい説明をすると、人の心の大半は「いま、ここ」に無いことで占められているので、「いま、ここ」にある体の感覚に注意を集中して、体の感覚に注意を集中すれば、「いま、ここ」に無いことについての思考が(短時間であっても)停止して、あなたは「いま、ここ」に無いことから解放されますよね、「いま、ここ」に無いことから解放されるということは、今までになかった体験ですよね、いままでにない体験は、あなたに新しい視点を提供するでしょう、そうすれば、いまここに無いことに起因する不適応や不安などのストレスへ効果的に対処するヒントが得られるのではないでしょうか、という説明になります。
ここで気を付けていただきたいのは、ヒントの受け取り方は人それぞれであってよく、正解はないということです。ですからマインドフルネスは、「こうしなければならない」という考え方の対極に位置します。
経験から、こうするとこうなるよ、ということは言えますが、しかし起こった変化をどのように受け止めるかは、その人自身が行うことなのです。
そして、いまここに無いことに起因する不適応や不安などのストレスへの対処がうまくできるようになると、私は私のままでいてよいのだ、という感覚を得ることにもつながります。
「私は私のままでいてよいのだ」という感覚とは、あれをしなければいけない、あれがないから私はうまくゆかないんだ、という考え方を、必ずしも選択してなくともよいのだ、という視点を得ることです。
この考え方にたどりつくためのキーワードが「やさしさ」です。
たとえばあなたに「あれをしなければならない、あれがないから私はうまくゆかないんだ」という考えが心の中にあるとします。
「あれをしなければならない、あれがないから私はうまくゆかないんだ」という考え方が心に浮かんだ時に、そのような考え方があることを認めたうえで、それについて、自分はそうしてもよいし、そうしなくてもよい選択肢があると「やさしさ」をもって考えてみることは、「習慣的な自動操縦状態」を脱出するにとつながります。
「しなければならない」という、自分にとって義務を課す、厳しい考え方を取らない考え方もあるのだと気付けば、自分のめざすものについて「別の対処方法」があることにも気付きます。
これが「やさしさ」をもって行うことが、とても大事な理由です。
自分に「やさしさ」をもって接することで、「習慣的な」考え方、対処方法を見直すことにつなります。
他者に対して優しいようにふるまうこと(「自己呈示」と言います)は、人付き合いの中でメリットがありますから、優しそうにふるまう人はたくさんいます。
優しそうにふるまっているだけですから、本質は優しくなくて、自分にもやさしくない、ということも当然あり得ます。まずは自分へやさしく接してみましょう。やがて他者にも自己呈示ではなく、やさしく接することが出来るようになります。
「あれをしなければならない、あれがないから私はうまくゆかないんだ」という思考があることを認めたうえで、そのように考えることもできれば、そのように考えないこともできそうだ、という心理的態度を獲得したならば、あなたは自由になります。
1つしかなかった選択肢が少なくとも2つに増えます。
「あれをしなければならない」と思考していたとしたら、「あれをしない自分」は、「しなければならないことをしない悪い自分」になってしまいします。「しなければならないことをしない悪い自分」と感じることは心を疲れさせ、結果として「あれをしなければならない」ことを達成する意欲をなくしてしまうことになります。
自分に優しくすることは、自分を甘やかすことではなくて、自分の自由な選択を認め、選択肢を増やすことによって、結果として自発的な行動を促進する効果が期待できます。
自分にない何かを手に入れる必要はありません。
そのような心理的な態度を獲得したあなたは、自由になり、自分にも他者にも寛容になり、周りからは魅力的に映るでしょう。
どうなるか試してみよう、という態度がマインドフルネスを継続する秘訣にもなります。
トレーニングやエクササイズと同じで、自分で継続してやってみなければ効果は感じられません。
好奇心をもてば継続することが多少なりとも苦でなくなります。好奇心を持つことによって自分の体や感情の変化にも敏感になります。つまり感受性が強化されます。
自分への感受性が強化されれば、他者が感じていること考えていることへの感受性も強化されます。他者への感受性が高まることが、お見合いや交際に、さらには結婚後の生活に役立つことはご説明するまでもないでしょう。
マインドフルネスの原型は仏教瞑想ですが、「やさしさ」「やさしく自分とあつかう」という考え方が、マインドフルネスをマインドフルネスたらしめている、と言ってもいいかもしれません。
「やさしさ」「やさしく自分とあつかう」という観点を重視することから、マインドフルネスは、セルフコンパッションやさまざまな心理療法にも波及しています。
どのように行うのか(1)準備運動
朝起きたときと夜寝る前に椅子に座ってする瞑想を10分程度行います。
これとは別に、一日2回3分程度時間が取れるときに(1分でも構いません)同様の瞑想を、こちらは立ったままでも座ったままでも構いませんので行います。
瞑想は、空腹時に行うことが原則です。満腹時には意識を集中する呼吸(腹式呼吸)がスムーズにできないからです。
最初に準備運動を行ないます。
座ってする瞑想は、背筋を伸ばした状態で呼吸しますので、その状態で呼吸を効果的に行うために行います。
息を吐くときは、前かがみになったほうが楽です。息を吸うときは、前かがみから体を戻した方が楽に息を吸えます。呼吸としてはこのようにした方が効率的ですが、体を動かしていると、集中力が働きません。そのため体を伸ばした状態で息を吐ききり、力を抜くことで息を吸うことを、事前に体に記憶させるため、と考えてください。
やり方を説明します。
右手と左手の4本の指の内側を重ね合わせて、組んだ手を頭の上へもってゆきながら一歩足を踏み出し、踏み出した足に体重を乗せて、腰を前に押し出す感じで体を伸ばします。
体を伸ばした状態で、ゆっくりお腹をへこませながら、力まないで息を吐ききります。
息を吐ききったらゆっくりお腹の力を抜いて、お腹が復元することに任せます。この時に空気が自然と肺に入ってきます。体の力を抜いて腕を下げてください。右左一歩ずつやってください。
腹式呼吸は、腹をへこませ、それを腰の筋肉が支えることで息を吐きます。そのことを感じながら行ってください。息を吐くときには腹をへこませて息を吐いていること、この時必然的に力が入ります。
息を吐ききったら腹部の力だけでなく体全体の力を抜いて、へこませた腹部が元に戻り息を吸うことを感じることがこの準備運動の目的です。
腹部だけでなく体全体の力を抜く感覚を養うことも瞑想では大事です。
次に、力を抜いて首を回してください。回している首に感じる感覚に注意を向けながらやってください。
首の次は、腕は下げたまま、肩に力を入れて肩を上げて、力を抜いて肩を下げる、これを2、3回繰り返してください。その後は腕は下げたまま、肩だけを前回りに回し、さらに後ろ回りに回してください。
この時も回している腕の感覚に注意を向けてください。
準備運動は、ほかにもありますが、初めて取り組む方はこのくらいで十分です。
同様なエクササイズは、マインドフルネスストレス低減法MBSRでは「ヨーガ瞑想法」として、マインドフルネス認知療法MBCTでは「マインドフルなストレッチ」として行われています。
どのように行うのか(2)座り方
手軽に取り組めるよう椅子に座ってやりましょう。座禅経験のある方は、それでもよいです。
深く腰掛けず、お尻の骨の下端部を椅子の座面の前半分から1/3にちょこんと乗せる感覚で、股関節の間にお腹をめり込ませるイメージで腰をまえに押し出して、背骨を伸ばし、肩の力を抜いてください。
手は、軽く握ってもいいですし、開いたまま甲を下にしておいても構いません。ひざの手前に自然において、肩の力を抜いてください。
腰に、腰から上の体重が真上から乗っかっていれば、最小限の力で姿勢を維持できます。気道がまっすぐになるので呼吸(空気の出入り)がスムーズになります。このような姿勢を目指してください。
自分の姿勢がどうなっているのか?
姿勢が楽に維持できるようになっているのか?
呼吸がスムーズにできる姿勢になっているの?
ということを感じ取ること自体も、マインドフルネスです。
腰を立てる姿勢となるので腰への負担はかかります(アイソメトリックストレーニングをするようなものです)ので、ここでも無理せず、腰痛にならない範囲内(時間)でやってください。
どのように行うのか(3)呼吸に注意を集中します
眼を閉じて行います。
手のひらを横にして、親指の先を臍に当ててください。そのとき小指を中心とした当たりが丹田です。腹式呼吸はこの丹田を意識して行ってください。
ただし無理に呼吸をすることはしないでください。
イメージとしては寝息のような自然な呼吸を目指してください。
最初、2回から3回意識的に細く長く息を吐いて、吐ききったら自然に腹が戻って空気を吸い込むことを感じてください。
次に、寝息のような自然な呼吸を心掛けながら、次のように心の中で唱えてください。
「いま私はここにいます。昨日のことも今日これから起こることもいまここで起こっていません。私は、これからの10分間は、いまここで私が感じる体の感覚に注意を集中します。」
このように唱えた後、お腹の動きに注意を集中しながらお腹の動きと息に注意を向けて、腹の動きと息について”実況中継”してください。
正解はありません。
たとえば、「息を吐いている吐いている」でもいいですし、「腹がへこんでいる、息が吐きだされている」でもいいです。感じたことを言葉にしてください。
息を吐き終わったら、同様に、息を吸っている状態について実況中継してください。
たとえば「腹の力が抜けて、腹が膨らんでいる」とか「腹が膨らんで空気が入ってきている」などでです。
人は息を吐くときには腹をへこませます。その時背中と腹で圧迫して空気を押し出しています。それらの力と、それに伴って入力される足や肩力も意識的に抜いてゆきます。
これを息を吐くとき、吸うとき3回ずつくらいやってください。
これは、腹の動きと息の出入りに注意を向けるための準備運動です。
マインドフルネスの効果が出るためには、呼吸による腹の動きへ注意を集中して、腹の動きを感じ取とることと腹の動きを言葉で確認することが「シンクロ」する必要があります。
感覚と言葉が「シンクロ」した時が、あなたの意識が「いま、ここに」いる状態です。過去のことも未来のことにも心が向かっていない状態です。
感覚と言葉を「シンクロ」させるには、単純な言葉のほうがやりやすいので、息を吐いている間は、腹の動きに意識を向けて「ちじみ、ちじみ」と言って腹の動きを言葉で確認します。これをラベリングと言います。
腹の動きに意識を向けて、動きを感じ取ることをサティと言います。
息を吸っている間は、腹の動きに意識を向けて「ふくらみ、ふくらみ」とラベリングします。
最初は言葉、ラベリングの独り歩きになって、腹の動き、息の出入りに注意を向け続けることが出来ません。
それどころか、お腹の動き、呼吸から注意がそれて別のことを考えてしまいます。それが自然なこと、普通のことなので、自分には難しいと考えないでください。
この状態が、あなたが「いま、ここ」にいない状態です。
簡単なことのように思えても、「いまここにある体の感覚」に注意を向けることは、最初は、誰にとっても難しいことなので、自分には向かない、などと考える必要はありません。
誰にとっても難しいをことに取り組むからこそ、効果があります。
注意がお腹の動きからそれたことに気がついたら、「体を感じることに注意を戻します」と唱えてお腹の動きに注意を戻します。
私は「いま、ここ」に無いことが想起されてときには「意識が〇〇に向かった」と自分に言って、元に戻します。
マインドフルネスは、「それてしまった注意を戻す訓練」だと理解してください。注意を戻す訓練をするのですから、日常生活での注意力も当然に強化されます。
ゆっくりあせらず続けてゆくことで、呼吸による副交感神経の活性化より安静効果がもたらされ、言葉がガイドとなって体を感じることができるようになります。
姿勢が安定して、無意識のうちに体に入っている力が抜けて、自然な呼吸ができて、呼吸に無理なく注意が集中し、息の出入りと腹のへこみふくらみを感じて言葉による確認と調和する(シンクロする)ようになると、時間の感覚が変化し、耳が聞こえなくなるように感じることがあります。
この感覚は、集中力が高まっていることによるものです。私も経験しましたし、ワールポラ・ラーフラさんという欧米に仏教瞑想を紹介した方も同様のことを著書の中でいわれています(ブッダが説いたこと 岩波文庫)
朝晩の10分間の座ってする瞑想に「集中」して取り組めるようになったら、日常生活の合間に「3分間」時間をとって、立ったままでもよいですし、椅子に座ったままでもよいので、腹の動きと息の出入りに注意を向けて、「腹を押しながら息を吐いています」「力を抜いています」という実況中継でもいいですし、「ちぢみ、ちじみ」「ふくらみ、ふくらみ」どちらでもよいので、言葉をガイド、先導役にして、腹の動きと息の出入りに注意を集中してください。
緊張状態を解きほぐすとともに、「いま、ここ」にいる自分に意識を戻すことが出来ます。
マインドフルネスは、頭で理解するものではなく、体が学ぶもの、という性格が強いものです。トレーニングやエクササイズと同様です。
やってみて自分で感じてみてください。自分で感じること、自分の感覚を知ることが第一歩です。
体の感覚とのつながりを感じることができたなら、日常の中で緊張を感じたときなどに、「腹を押しながら息を吐いています」「力を抜いています」という言葉のガイドとともに、呼吸へ注意を向けることで、自分を緊張から解放することが出来るようになります。
人は、認知した情報に対して、快適な、不快な、中立的な、という3つの反応をすることが報告されています(FriedmanRS,Foster J)。
不快な反応の場合には、体に緊張が生じます。この緊張を察知することにより、意識的に緊張を解放することもできるようになります。
マインドフルネスの源流となった仏教瞑想では、体に生じる感覚として、快適な=楽、不快な=苦、中立的な=不苦不楽の3つの感覚を観察します。これを受の随観といいます。
効果が実感できるまで多少の時間はかかります。
筋トレやエクササイズも1回おこなったから、効果が実感できて、その効果が持続する、ということはありませんよね、それと同じです。
続けることですこしずつ効果が実感できます。
効果はご自身で実践して感じて、評価してください。
それもまたマインドフルネスの本質です。
MBSRもMBCTも、継続することを、効果を実感するための必須のものとしています。