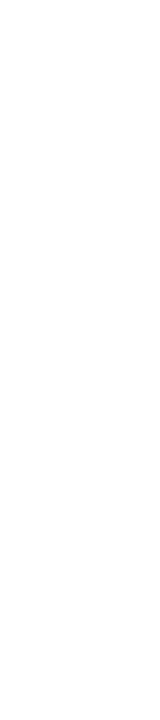質問:そもそもマインドフルネスは婚活に有効なのですか?
- 婚活のコツ
- 婚活のお悩み
目次
- 回答:しっかりやれば有効
- 婚活にはどんなメリット期待されるのか?
回答:しっかりやれば有効
しっかりやれば有効です。
「しっかりやれば有効」ということになると、「しっかりやる」ということの内容が重要になってきます。
「しっかりやる」とは?
1.一日の中で時間を決めて、定期的継続的に行う
2.時間内はマインドフルネスに集中してやる
の2点になろうかと思います。
1.一日の中で時間を決めて、定期的継続的に行うこと
マインドフルネスは、わかりやすく言うと「頭の機能を転換」するトレーニングです。
瞑想を通じて、「頭の機能を転換」するトレーニングをおこない、瞑想中に「頭の機能を転換」し、その状態が瞑想以外の日常生活の中でも機能するようにするようになることが理想的です。
まずそのためには、一日の中で時間を決めて継続的に取り組むことが必要です。
2.時間内はマインドフルネスに集中してやること
物事の在り方として当然のことですが、1日10分トレーニングする人よりも1日30分トレーニングする人のほうが、トレーニングの効果はより期待できると考えられます。
とはいっても、30分間トレーニングはしていても、集中していない人よりも、10分間であっても集中して取り組む人の方が効果が出る可能性は十分あります。
そもそもマインドフルネスは「注意集中」の訓練ですから、長時間やっても集中しないと効果は期待できません。
マインドフルネスに集中するとは、端的に言うと、マインドフルネスに取り組む時間内は、心の中からマインドフルネス以外のことがらを「捨てる」「締め出す」「考慮しない」「関心を向けない」という態度をもってマインドフルネスに取り組むことです。
たとえ10分でもこれが出来れば、効果は上がります。
しかし、あらかじめ申し上げておきますが、10分間継続して集中状態が維持できるとすれば、その方はすでに相当な「上級者」です。
このレベルになれば、自己の心の状態を観察して、複数の瞑想を組み合わせて行うことも可能です。
30分一生懸命やっても集中できている状態が1、2分実現できればうまくできていると言えるでしょう。
「頭の機能の転換」エネルギー消費の低減
人間はリラックス状態のときに、デフォルト・モード・ネットワーク(DMN)という脳の情報網が活発になるそうです。
リラックス状態なので、休憩していることになるはずですが、実はDMN状態は極めて脳のエネルギー消費が高い状態だそうです。気分はリラックスしながら、脳はたくさんのエネルギーを消費、つまり一生懸命働いている、ということになります。
最近の研究で、マインドフルネスはDMNのエネルギー消費を低減する効果があるとわかってきたそうです。
さらに、10年以上のマインドフルネス経験のある人にはDMNの変化が認められることもあるそうです。(久賀谷亮 「最高の休憩法」ダイヤモンド社より)
DMNのエネルギー消費を低減するとは?
ここでは自分の経験からお話します。
マインドフルネスは、呼吸や運動、体に感じる感覚へ意識を集中し、細かく観察することによって自分の「いまここでの変化」に注意を集中することによって、今ここには無いこと(=過去の出来事や未来のこと、ここではないところのこと)に意識が向かう思考を停止し、思考を停止することによって感情の生起を止めることが出来るようになることが、到達度合いの一つの目安になります。
たとえば呼吸に注意を向け、呼吸に伴う腹のふくらみとへこみに意識が集中し、それを言葉で確認すること(ラベリング)がシンクロすると、思考は停止します。思考が停止すると、感情の生起が停止します。
感情の生起が停止すると「こんなに楽になるのか」という状態を経験できます。
久賀谷さんは、言及されていませんが、感情の生起の停止による「こんなに楽になるのか」という状態が、DMNのエネルギー消費を低減している状態であると私は考えています。
また、感情の生起を停止することにより、あれこれ悩むことが少なくなり、あれこれ悩まないことで思考の整理が進む、というメリットもあるでしょう。
人が迷うときには、感情につき動かされた考え方や欲求と、意識的論理的に導き出した考えが混然としている状態ととらえるならば、感情に突き動かされた考え方や欲求がなくなれば、答えは出しやすくなるでしょう。
あれこれ想像をめぐらした結果、疲れを感じたり気分が落ち込んでやる気がなくなった、という経験は多くの方がお持ちだと思います。
この状態がDMNが活動して、心があれこれと考えて、それに伴い感情が生起し、脳が大量のエネルギーを消費している状態だと考えてよいと思います。
DMNの活動の抑止は、DMNとシーソーのような関係にあるワーキングメモリーが活性化することによるとする考え方もあるようです(社会脳ネットワーク入門、芋阪直行・越野英哉、新曜社)。
「頭の機能の転換」思考の質的変容
人間はその認知構造上、自分の体に起こった感覚も外部の出来事も直接体験できません。
神経と脳の機能を思い起こしていただければ、ご理解いただけることなのですが、グレゴリー・ベイトソンさんが、わかりやすい説明をしているので引用します。
「誰かに足を踏まれたとき、私が経験するのは、”彼による私の足の踏みつけ”そのもではなく、踏まれてからややあって脳に届いた神経報告をもとに再構成された”彼による足の踏みつけについての私のイメージ”にほかならない。外界の経験には常にある特定の感覚器と神経危経路が介在しているのである。その限りにおいて、ものとは私の想像物であり、ものの経験は主観的であって客観的ではない。」
さらにこのようにも言っています。
「自分たちが”見て”いるイメージが、脳なり精神なりによって作り出されれることは誰でも知っているが、このことをただ知識として知っているというのと、実際に感得しているというのでは大違いである。」(精神と自然 グレゴリー・ベイトソン 佐藤良明訳 思索社)
瞑想指導者の地橋秀雄さんは、瞑想の進め方について、著書の中で次のように言われています。
「何をもって基本が出来たと判断すればよいのでしょうか。それは、法と概念の仕分けができることです。(中略)思考を止めて厳密に法としての事実のみに気付く状態にならなければ、その先には進めません。」(ブッダの瞑想法 地橋秀雄 春秋社)
地橋さんの言われていることを、ベイトソンさんの言われていることを考え合わせると、
『人間が認知したものは全て頭の中で作られたイメージにすぎないが、神経系をとおって脳に到達した情報=実在する事実=「法」と、その情報に反応して脳が(自分なりに)作り上げた「概念(的理解)」を仕分けできるようになることが瞑想の基本』
と解釈することが出来ます。
このことは、ベイトソンさんの言う「自分たちが”見て”いるイメージが、脳なり精神なりによって作り出されれること」を、「実際に感得している」状態を作り出すこと、と言ってもいいかもしれません。
「頭の機能の転換」のまとめ
1.感情の生起が停止または抑制されることで、DMN起動時の能のエネルギー消費が抑制されること(楽になる、疲れなくなる)
2.脳に到達した情報と、その情報に反応して形成される概念的理解を仕分けできるようになる(訓練をする)
3.上記2.の訓練により、1.の機能転換がすすみ、脳には余力が生まれ、思考の整理が進む
久賀谷さんの指摘されている「10年以上のマインドフルネス経験のある人にはDMNの変化が認められる」とは、このようなことではないかと考えています。