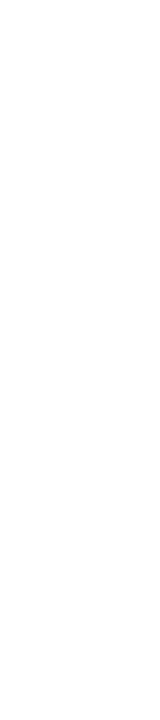恋愛未経験・あゆみのアラフォー婚|第3章
- 成婚者エピソード
- 男性向け
- 女性向け

結婚願望の薄い彼と、恋愛未経験のあゆみ
真剣交際に進んだあと、あゆみ(仮名・41歳・薬剤師)と彼・まさき(仮名・44歳・会社員)は、週に一度のデートを重ねていた。渋谷での食事や映画、夏には花火大会へも出かけた。まさきは穏やかで誠実な人だった。あゆみの誕生日には、心のこもったプレゼントをくれた。だが、彼の中にどこか“遠さ”を感じることがあった。
「彼、自分の話をほとんどしないんです」
そう打ち明けるあゆみの表情は、少し切なげだった。まさきは自分の内面にあまり興味がないように見えた。まるで、自分を傍観しているようだ──そう感じたこともあったという。
彼の自己肯定感の低さを、あゆみは痛いほど理解できた。かつての自分がそうだったからだ。
自分に許可を出すということ
私とのセッションの中で、あゆみはこうつぶやいた。
「昔から、自分の居場所が欲しかった。誰かに“ここに居ていい”と言ってほしかったんです」
少しの沈黙のあと、私は答えた。
「本当はね、それを自分で言えばいいんですよ。大人の女性は、自分に“居ていい”と許可を出せる人のことです」
あゆみは目を見開いた。「自分に許可……」
「そう。何かをしなきゃ、とか、認められなきゃ、とか思わなくていい。ただ、自分に“それでいい”と許す。それができる人が、誰かと対等に愛し合えるんです」
あゆみは深く息を吸い、「私は私のままでいいんだ」と心の中で繰り返した。その言葉を意図し続けようと、心に誓った。まさきとの関係の中で。
「私はまさきさんと結婚する」でいい
あるセッションの日、私はあゆみに言った。
「彼の結婚願望がどうであろうと、“私はまさきさんと結婚する”でいいんです」
余計なことは考えなくて大丈夫。過剰な期待も、“べき”も要らない。ただ、「私は結婚したい。あなたはどう?」でいい。
そのアドバイスを受けたあゆみは、次のデートで勇気を出して切り出した。彼は少し驚いた顔をしたが、真剣に聞いてくれた。そして彼自身の戸惑いを語った。「結婚のイメージがまだうまく掴めないんだ」
以前なら「やっぱり無理かも」と引いていたあゆみだったが、その日は違った。彼の目を見て言った。「それでも、私はあなたと生きてみたい」
“彼を信じてもいい”が生まれた瞬間
まさきの生い立ちは、少し特別だった。父親とは一度も暮らしたことがなく、母の実家で祖母の介護をする伯母たちと共に育ったという。家庭の中で“男性”という存在が欠けていた。
あゆみは、そんな彼の過去を責めず、ただ聴いた。デートの帰り、ネットカフェの個室で、彼が語る幼少期の思い出に耳を傾けた。彼は時々、涙ぐんだ。あゆみはそのたび、そっと手を握った。そこにジャッジはなく、ただ温かい沈黙があった。二人の距離が確かに近づいた気がした。
「彼を信じてもいい」──その感覚が、初めて自然に生まれた瞬間だった。
覚悟を決めさせてあげる
数週間後、彼は「来月、一度成婚退会して、その後ゆっくり交際を続けたい」と提案してきた。あゆみの胸に不安がよぎる。彼は本当に結婚する気があるのだろうか?
以前、彼が「早く一緒に棲みたい」と言ったときの、どこか曖昧なニュアンスが蘇った。あゆみはきっぱりと決めた。曖昧なままでは終わらせない。
「彼の本意を、自分の言葉でちゃんと確認した方がいいよ」──私の助言を胸に、あゆみは向き合うことを選んだ。
「このままずっと付き合い続けるのは無理だからね。いつか別れるか、結婚するか。私は、まさきを幸せにしたいから結婚したい」
その言葉に、彼の目から涙がこぼれた。
私はあゆみに言った。「ペットを飼ったことありますか?」
あゆみ「えっ、ペット?」
「たとえば、犬のしつけと似てるんです。覚悟を決めさせてあげるには、あなたが先に覚悟を決めること」
あゆみは笑いながら頷いた。確かに、手綱を握るのは女性の役割かもしれない──そう思った。
彼の母との出会い、そして“居場所”
彼の母は、思っていた以上に優しい人だった。「籍は早めに入れた方がいいわよ」と穏やかに言ってくれた。あゆみはその瞬間、胸の奥が温かくなった。恐れていた“拒絶”はなかったのだ。
「居場所が、もう一つ増えた気がします」
そうつぶやいた彼女の笑顔は、どこか安心した子どものようでもあり、大人の女性の自信にも満ちていた。
あゆみのアラフォー婚は、“誰かに選ばれる”物語ではなく、“自分で選んで生きる”物語に変わっていった。